Redditで、Rlawless5さんが過去に投稿した、初心者への教訓となる素晴らしい記事の内容をご紹介します。
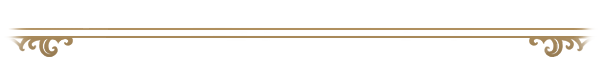
(※以下引用)
もし上級者のプレイ配信を視聴しているのならば、「バリュー(Value)」という単語を耳にしたことがあると思います。
この「バリュー」とはどんな意味なのでしょうか。
ハースストーンは、手札カードの枚数が限られるゲームです。
よって、各カードをより有効に活用するプレイヤーが勝利に近づきます。
通常は、所有するカード1枚で相手のカード1枚を処理する行為が繰り返されます。
ですが、時として1枚のカードが相手の2枚以上のカードを処理することがあります。
相手がミニオンカードを2枚使用して、2体のミニオンを召喚したとしましょう。
そこで、あなたがフォーク・ライトニング(2体の敵のミニオンに2ダメージ)でその2体を破壊したら、1枚の呪文カードで相手の2枚のミニオンカードを処理したことになります。
この場面でのフォーク・ライトニングは有効に活用されたとみなされます。
なぜならば、1枚で2枚を処理したあなたが1枚分のカード・アドバンテージを得たからです。
所有するカードを1枚消費して、相手の2枚のカードを処理することは「2 for 1」と呼ばれます。
所有するカードを1枚消費して、自身が2枚のカードを得ることも「2 for 1」と呼ばれます。
いずれも、相手よりも1枚分のカード・アドバンテージを得る行為です。
カード・アドバンテージを得ると、それだけ自由に使えるカードの枚数が相手よりも多くなります。
自由に使えるカードが多いほどプレイの選択肢が広がり、自分が有利となるようなアクションを起こしやすくなります。
このようなアドバンテージを与えてくれる可能性が高いカードは、価値が高いカードです。
冒頭で述べた「バリュー」という単語は、その価値の指標を示すものです。
「バリューが高いカード」とは、プレイヤーにアドバンテージを与えやすいカードであることを意味します。
特殊能力を持たないチルウィンドのイェティの人気が高い理由は、「2 for 1」を実現しやすい、高い「バリュー」を持つカードだからです。
第4ターンに召喚される4/5のチルウィンドのイェティは、それまでに召喚されたコスト3以下の敵のミニオンを倒し、かつ生存できる可能性が高いミニオンです。
チルウィンドのイェティが1体の敵のミニオンを倒した後、場に残ったとしましょう。
そのチルウィンドのイェティへとどめを刺すのに、相手が呪文カードやもう1体のミニオンの犠牲を必要とするならば、チルウィンドのイェティは「2 for 1」を成立させることになります。
アジュア・ドレイクは、召喚されると同時にプレイヤーへカードを1枚与えます。
この時点で、所有するカードを1枚消費して1枚のカードを得る「1 for 1」が成立します。
さらに呪文ダメージの能力や4/4のステータスが、少なくとも相手の1枚のカードを消費させるでしょう。
最低でも「1 for 1」、ほとんどのケースで「2 for 1」を成立させるから、「バリュー」が高いことになり、人気も高くなるのです。
武器カードがよく用いられるのも、それらの「バリュー」が高いからです。
ハースストーンのほとんどの武器は、2体以上の敵のミニオンを倒す力があります。
1つの武器で2体の敵のミニオンを倒せたならば、その武器を生産した武器カードは「2 for 1」を成立させたことになります。
何の考えもなく武器で相手のヒーローを攻撃するのは、もったいない武器の使い方と言えます。
なぜならば、相手のヒーローを攻撃しても相手のカードを処理することはできず、ミニオンを倒すことで得られるはずのカード・アドバンテージを放棄することになるからです。
人気が低いカードは、もちろん「バリュー」が低いカードです。
コスト1のミニオンたちの評価が総じて低いのも、「バリュー」の低さが理由です。
 コスト1のミニオンは、相手のカードを処理できるような能力を持たず、攻撃力か体力の値が1であるものばかりです。
コスト1のミニオンは、相手のカードを処理できるような能力を持たず、攻撃力か体力の値が1であるものばかりです。
攻撃力が1では相手のミニオンを1体も処理できないまま倒される確率が高く、体力が1ではカードを消費しないヒーローパワーで倒されてしまいます。
ミニオンが相手のカードを何も処理しないまま倒されると、ただ1枚のミニオンカードを消費しただけの「0 for 1」が成立することになります。
「2 for 1」が1枚分のカード・アドバンテージを与えるのに対し、「0 for 1」は1枚分のカード・アドバンテージを失わさせます。
コスト1のミニオンカードの多くは「0 for 1」を実現しやすいために「バリュー」が低いのです。
ダメージを与える呪文カードを相手のヒーローに対して使用すると「0 for 1」です。
体力を回復する呪文カードを自分のヒーローに対して使用すると「0 for 1」です。
盾持ちの召喚は、何らかの効果と組み合わせなければ「0 for 1」が確定します。
カード同士の相乗効果をあまり期待できない闘技場では、カードを効率よく運用し続けることが重要となるため、「0 for 1」が発生するごとに勝率は低くなるでしょう。
初心者にありがちなのは、上級者が紹介するデッキやカードランクを盲目的に見習うことです。
上級者が意図するところを理解しないまま、提示された内容をただ模倣しているだけのプレイヤーは少なくありません。
形式だけを模倣しても、上級者と同じ結果を得られるわけではありません。
平均以上のプレイヤーを目指すのならば、カードの選択がどのような理由で行われているのかを正しく理解せねばなりません。
今回の投稿が、その理解の手助けとなることを願っています。
なお、以上まで説明してきた内容は主に闘技場での対戦の心得ですが、通常の対戦でも活用できるところが多分にあると思います。
(※引用ここまで)
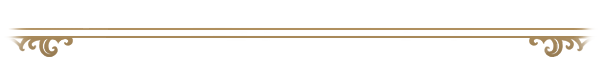
テンポ・アドバンテージという、カード・アドバンテージと同等に重要視される要素があることを追記いたします。
簡単に説明すると、カードを有効に活用するとカード・アドバンテージを得て、マナを有効に活用するとテンポ・アドバンテージを得ます。
一般的には、テンポ・アドバンテージで有利に立つ側が、相手のヒーローをより速く倒すことになります。
速攻型のデッキは、このテンポ・アドバンテージを序盤で大きく稼いで、短いターンで相手を倒します。
カード・アドバンテージはテンポを持続する手段です。
カード同士の効果的な組み合わせを構築しにくい闘技場では、純粋なカード・アドバンテージとテンポ・アドバンテージが勝敗の鍵を握ります。
カード・アドバンテージを得ることに特化してカードの消費効率を良くしても、テンポで劣勢となって、そのアドバンテージを活かす前に倒されては意味がありません。
だから、闘技場のカード・ドラフトにおけるカードの選択では、各カードの「バリュー」とともにデッキ全体のコスト・バランス(マナカーブとも呼ばれる)が重要視されるのです。
高い「バリュー」のカードだけで構成したとしても、コスト・バランスが悪くてマナを消費できないターンが続けば、テンポ・アドバンテージが著しく損なわれることになります。
ぜひ、闘技場ではカードの効率とテンポの効率の両方に配慮してみてください。
Reddit (ハースストーン) – [Basics] Being able to distinguish a bad card from a good one


